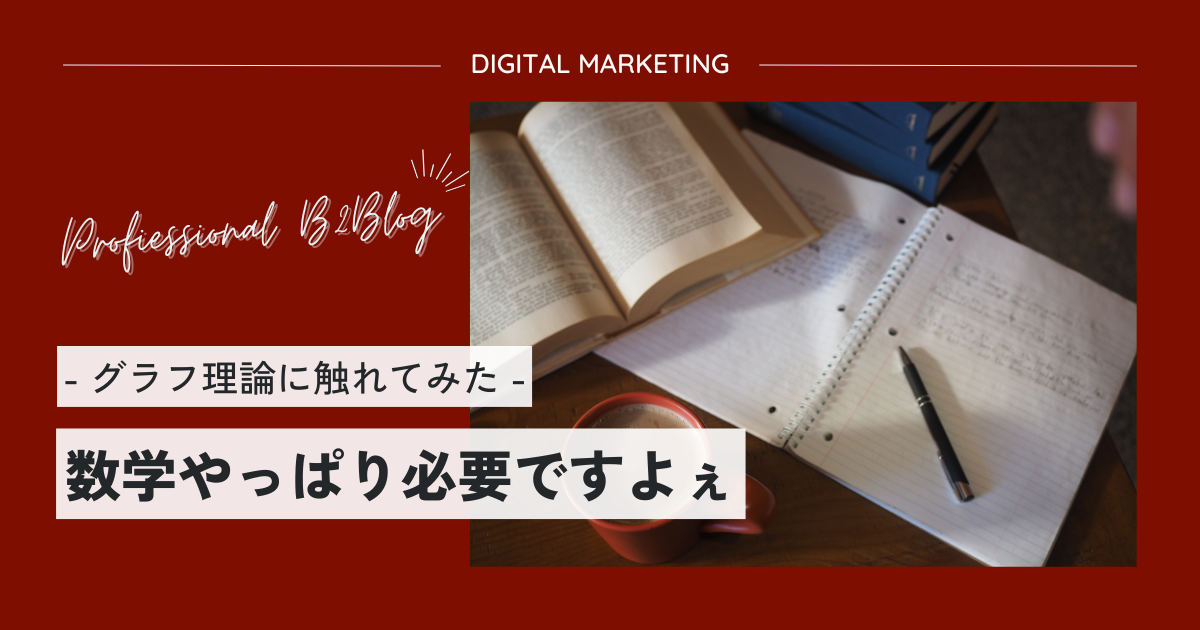リードの初期精度を上げていくために ~新入社員教育から見えてきたこと~
公開日時:2025/01/18
更新日時:2025/01/18
早いもので、2024年度も終わりに近づいてきました。週末は久しぶりに愛用のカメラを持ってスナップシューティングに出かけましたが、まだ春には遠いですね。そんな春の訪れを待つ間、この1年を振り返ってみようと思います。
特に印象深かったのは、入社以来初めて新入社員の教育担当を任されたことです。私自身が入社して6年目。まさか自分が誰かを指導する立場になるとは、と身が引き締まる思いでした。当初は戸惑いもありましたが、振り返ってみると、この経験は私自身の成長にとっても大きな転機となりました。
新入社員教育で見えてきた、伝えるべきこと
教育担当になって最初に悩んだのは、何をどの順序で教えていくかということでした。デジタルマーケティング部門の業務は多岐にわたります。SEO、リスティング広告、コンテンツマーケティング...。しかし、それらの前に伝えるべきことがあると考えました。
思い返せば、私自身が入社したての頃は目の前の技術や手法の習得に必死でした。しかし、実際の現場で本当に必要だったのは、もっと基本的な理解だったのです。そこで今回は、あえて技術的な内容は後回しにすることにしました。
まず重視したのは、自社のビジネスモデルの理解です。B2Bビジネスにおいて、製品やサービスを売り込む前に、まずはお客様の課題を理解することが重要です。そのためには、自社が提供する価値を深く理解している必要があります。
新入社員には、最初の1ヶ月は営業同行や製品研修に多くの時間を割いてもらいました。それ以降も時には請求の流れや契約書なども見てもらう機会を設けました。一見、デジタルマーケティングとは無関係に思える内容かもしれません。しかし、「なぜデジタルマーケティングが必要なのか」という本質的な問いに向き合うためには、このような過程が不可欠だったと思います。
デジタルマーケティングの「二つの顔」
新入社員との対話を通じて、改めて気づかされたことがあります。それは、自社におけるデジタルマーケティングと、世間一般でのデジタルマーケティングには、微妙な違いがあるということです。
例えば、一般的なデジタルマーケティングの教科書では、SNSやインフルエンサーマーケティングが大きく取り上げられています。確かにこれらは重要なチャネルですが、私たちのような製造業のB2Bビジネスでは、それらの手法の優先度は必ずしも高くありません。
むしろ重要なのは、ホワイトペーパーやセミナー、製品デモなど、お客様の意思決定に直接関わるコンテンツの制作と配信です。特に最近は、オンラインセミナーの需要が高まっており、その企画から実施、フォローアップまでの一連のプロセスを設計する機会が増えています。
この「違い」を理解することは、外部のパートナー企業とのコミュニケーションでも重要になってきます。施策の優先順位や予算配分を議論する際に、B2Bならではの特性を踏まえた提案ができるかどうかが、プロジェクトの成否を分けると実感しています。
基本に立ち返る:「ザ・モデル」との再会
新入社員教育の準備をしている際、久しぶりに「ザ・モデル」を読み返しました。発売から時が経っていますが、B2Bマーケティングの基本を考える上で、今でも色褪せない示唆に富んでいます。当時、上司から「この本は定期的に読み返すといい」と言われた意味が、今になってよく分かります。
読み返しの中で思い出したこととして特に印象的だったのは、「知識」と「知恵」の違いについて上司から指摘されたことでした。書籍から得られる知識は定石であり、雑誌やWebメディアから得られる知識はトレンドです。しかし、それらを実践の中で活かし、自分なりの知恵に昇華させていくプロセスが重要なのです。
新入社員には、読書をしただけで満足せず、必ず何らかのアウトプットを作るよう指導しています。例えば、読んだ内容を自社のケースに当てはめて考えてみる。あるいは、さらに詳しく調べたい項目をリストアップし、追加の研究を行う。このような習慣づけが、後々大きな差となって現れてくるはずです。
リード獲得の精度を上げるために
この1年の教育担当としての経験を通じて、改めて「リードの質」について考えさせられました。良質なリードを獲得するためには、私たち自身が「良質な理解」を持っている必要があります。
昨年は、いくつかの施策がうまくいかない経験もしました。原因を分析してみると、往々にして製品理解や業界理解の不足に行き当たります。デジタルマーケティングの技術は日々進化していますが、その根底にある「お客様理解」の重要性は変わらないのだと実感しています。
製品知識、業界知識、そしてデジタルマーケティングのスキル。これらを単独で高めるのではなく、有機的に結合させていく必要があります。新入社員と一緒に学び直す中で、この当たり前のことの重要性を再認識しました。
来年度は、この経験を活かしてリード獲得の精度をさらに上げていきたいと思います。そのためには、日々の業務の中で「なぜ」を問い続け、チーム全体で知見を積み重ねていく必要があるでしょう。
とはいえ、すべてを完璧にこなそうとするのではなく、時にはカメラを持って外に出て、気分転換を図ることも大切だと思っています。新しい視点や発見は、意外なところから生まれるものですから。
さて、そろそろ桜の開花も近いはず。今年は新入社員と一緒に、お花見がてらのフォトウォークを企画してみようかと考えています。仕事の話も、カメラの話も、きっと良い会話が生まれることでしょう。