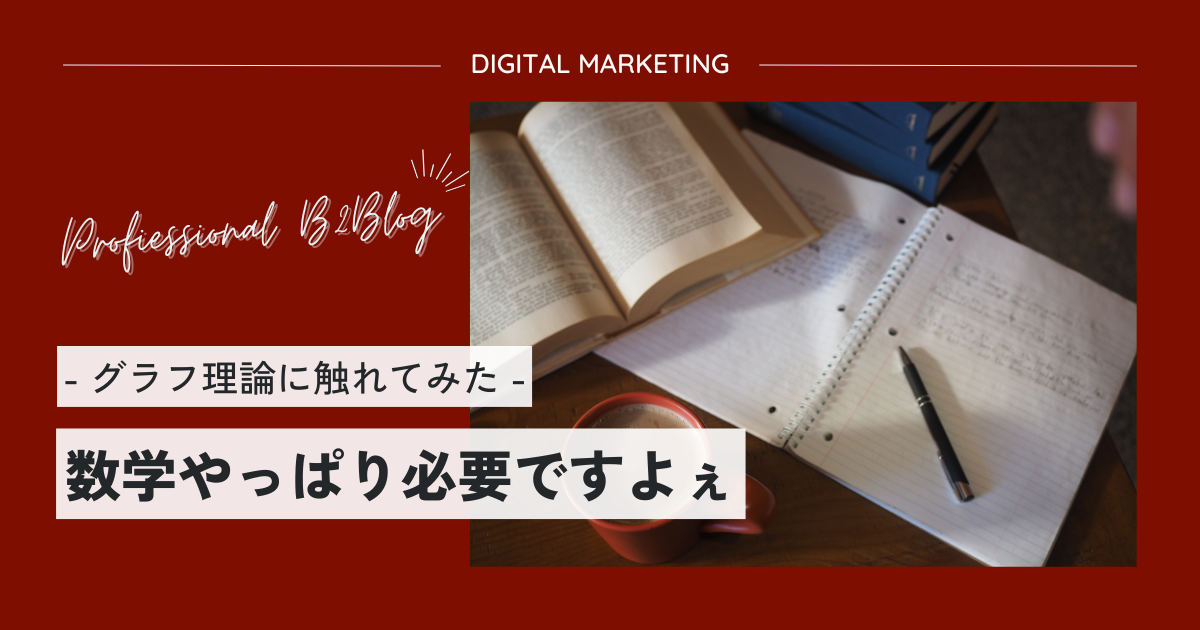新しいテクノロジーと向き合う私たちのこれから
公開日時:2025/01/11
更新日時:2025/01/11
この10年、がむしゃらに走ってきた
デジタルマーケティングの世界に飛び込んでから、早くも10年が経とうとしています。文系出身で、当時はHTMLすら満足に書けなかった私が、今では部署のリーダーとして若手の指導に当たっています。振り返ってみると、本当に目まぐるしい変化の連続でした。
リスティング、アフィリエイト、SEO 当時の最新技術を徹底して学んだ新人時代
入社当時、上司から「君には期待していない」と言われたことを今でも覚えています。確かに、ExcelのVLOOKUPすら使えない新入社員でしたから、無理もありません。でも、それが逆に私の原動力になりました。
毎晩遅くまでリスティング広告の入札単価の分析をし、アフィリエイト広告のクリエイティブを何度も何度も書き直し、SEOの基礎を必死で学びました。専門用語を理解するのに苦労し、データの見方も分からず、何度も壁にぶつかりました。それでも、少しずつですが成果は出始めていました。
コンテンツマーケティングに舵をきり、ユーザーのことをひたすら考え続けた
5年目くらいから、私たちの業界でコンテンツマーケティングという言葉が飛び交うようになりました。それまでのテクニカルなSEO対策から、より本質的なユーザー価値の提供へと、業界全体が大きく方向転換した時期でした。
実は、この変化は私にとって追い風でした。なぜなら、文系出身の私には「人の気持ちを理解し、それを言葉で表現する」というスキルが備わっていたからです。ペルソナを設定し、カスタマージャーニーを描き、ユーザーの悩みに寄り添うコンテンツを作り続けました。
技術的な理解は依然として必要でしたが、より重要なのは「人」を理解することだと気づいたのです。その気づきは、私のキャリアの転換点となりました。
埋め込みモデルからAIと途端に数学の世界が広がってきた!?
そして今、私たちは再び大きな変革期を迎えています。ChatGPTの登場以降、AIという言葉を聞かない日はありません。最初は単なる文章生成ツールだと思っていましたが、その本質を理解しようとすると、そこには深い数学の世界が広がっていました。
埋め込みモデル、トランスフォーマー、確率分布...。聞きなれない言葉の数々に、正直なところ戸惑いを感じています。数学が苦手だった私にとって、これらの概念を理解することは大きなチャレンジです。

追いかけられるようになったということなのか?
世界が変わってしまってるように感じる
以前は、新しい技術やトレンドを追いかける側でした。でも今は、追いかけられているような感覚があります。AIの進化のスピードは、私たちの学習速度をはるかに超えています。
毎朝、業界ニュースをチェックするたびに新しいAIツールや機能が発表され、その度に「もう追いつけない」という焦りを感じます。かつての私なら、新しい技術に胸を躍らせていたはずです。でも今は、その変化の速さに不安を感じることの方が多くなりました。
新しいものの出現に恐れおののき、忌避感を感じているのだろうか?
先日、若手社員とAIについて話していて気づきました。彼らは自然にAIを受け入れ、むしろ積極的に活用しています。対して私は、どこか警戒心を持って接していました。
この違いは何なのでしょうか。単純な世代間ギャップなのか、それとも私自身が知らず知らずのうちに保守的になってしまったのか。自分でも答えが出ません。
ただ、この「恐れ」や「忌避感」は、実は私たちの先輩たちも経験してきたものかもしれません。インターネットが普及し始めた時代、スマートフォンが登場した時代。そのたびに、人々は不安と期待を抱きながら、新しい技術を受け入れてきたはずです。
新しい毎日にむかって日々どのように立ち向かっていこうか
結局のところ、私たちに必要なのは「バランス」なのかもしれません。新しい技術を完全に拒絶するのでもなく、盲目的に受け入れるのでもなく。
私の場合、まずは自分の得意分野から始めることにしました。例えば、AIを使ってコンテンツのアイデアを出し、それを人間の感性で磨き上げる。数学的な理解は確かに重要ですが、それは徐々に深めていけばいい。
大切なのは、変化を恐れずに、でも慎重に、一歩一歩前に進むこと。10年前の私がそうだったように、今度は新しい技術と共に、また新たな挑戦を始める時なのかもしれません。
私たちは、テクノロジーと人間の接点に立つ「デジタルマーケター」です。だからこそ、技術の可能性と人間の価値観の両方を理解し、橋渡しをする役割を担っているのだと思います。
明日も新しい技術が生まれるでしょう。その度に戸惑い、悩むかもしれません。でも、それこそが私たちの仕事の醍醐味なのかもしれません。これからも、好奇心と謙虚さを忘れずに、新しい波に乗り続けていきたいと思います。